SSS(高校1年生)まちづくりとは
- 2024.05.29
- 授業
中間テストの最終日の試験後、2回目のSSS講座を実施しました。この講座でのテーマであるSDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」について具体的に学びます。誰もがどこかの街に住み、そこで生活しています。住む場所について、これまでは自分の選択ではなかったため関心の低い人もいるかもしれません。でも、住人どうしが笑顔であったり、散歩道が気持ち良かったり、ふとしたことで幸せを感じるということはありませんか。逆に不便を感じていることもあるかもしれません。まちづくりとは、私たちの生活に日々深く関わっているテーマであることを感じる講座となりました。
【1】「まちづくり」とは何か?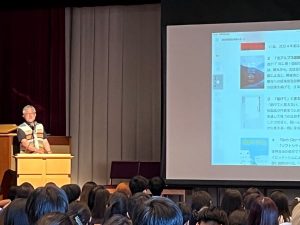
「身近な居住環境を改善」し、「地域の魅力や活力を高める」持続的な活動のこと
●ハード面とソフト面
交通や施設や防災計画などのハード面だけでなく、それをどうやって利用するか、公共空間はどのように共有するか、福祉を含めたソフト面での発想も必要になります。
●誰が関わっているのか
行政、市民、学生、専門家などなど、さまざまな立場からの関わり方があります。まちづくりは行政の仕事と思っていた人も多いと思います。でも実は誰もが関わることのできる分野でもあります。
恵まれた人も決してそうでない人も、街には様々な事情のある人たちが一緒に暮らします。様々な年代、障がいの有無、育児中など、そして自分もいつどのような立場になるかわからない社会です。どういった立場の人も幸せに過ごせることが大切です
⇓
様々な視点からまちづくりを考えることが必要
【2】教員はどのような視点からまちづくりを捉えているでしょうか
教員それぞれが興味をもった書籍やイベントから紹介します。
街は決してその枠組みだけが整っていればよいということではなく、あくまで人々がそこでどう過ごすか、快適に過ごせているかが大切です。人のためのまちづくりを「建築と都市計画はもっとソフトになる必要がある」と解説した本です。実際に著者のSim先生とも会った帖佐教諭は、同じビルのアパートでもそれぞれ個性のある部屋造り、海岸の石も形や大きさもいつもそこを歩き拾う人のことを考えてあえてバラバラに、こういったことから「自分だけの」という感覚を大切にしているスウェーデンのまちづくりの仕掛けについて話しを聞きました。これこそシビックプライド(愛着を持ち誇りを感じる)につながる取り組みです。
朴元教諭が育った東京の高田馬場では、子供のころに公園で酔っ払いや浮浪者が寝ているという光景があったそうです。それは現在になって思うと実は共に生きているという感覚だったかもしれません。そういった人々は街から排除された結果どこへ行ったのでしょう。この本は著者の奥田牧師がホームレスの支援活動を通して「困窮者支援とは『強い人が弱い人を助ける』ということではなく、弱い人間同士が共に生きることである」ことを見つめ直そうとした一冊です。
アムステルダム、バルセロナなどさまざまな都市の街の取り組みを紹介しています。この中で、坂下教諭も訪ねたことのなるアムステルダム、自転車で街を巡ると住んでみたらきっとワクワクするだろうなという感覚になりました。自転車優先、図書館、美術館、すべての取り組みを包み込むようにして、住民が街を誇りに思う気持ちを高揚させる様々な仕掛けがあったようです。まちづくりといっても様々な視点からのアプローチがあります。広く社会を見て、自分はどこで貢献できるか将来の専門を考えるということも良いかもしれません。
教員もまちづくりに対しての視点はさまざまです。そしてまちづくりは、それぞれ違う視点から取り組まれていることもわかりました。
【3】大阪公立大学 准教授 武田重昭先生講演について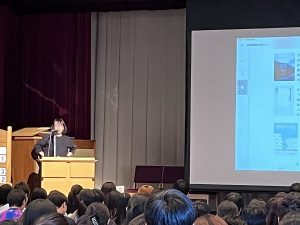
次回のSSS講座では、武田重昭先生の講演を予定しています。事前学習として知っておきたいことを学びます。武田先生は実際に第一線でまちづくりに関わる専門的な知見を持つ方です。そして先生のご研究の中にはまちづくりに関するワクワクするKeywordが登場します。自分だけが心地よく魅力を感じているのではなく、街全体が魅力的、そこに住む皆が心地よく生活できること、それがパブリックライフだとおっしゃいます。
大阪公立大学 生命環境科学研究科 緑地環境科学分野
住宅団地やニュータウン等の計画的に整備された集住環境におけるオープンスペースをはじめとする都市の緑地空間を対象として、その空間形態とそこでの生活行動や運営の仕組みとの関係性を分析し、保全・継承すべき緑地環境の特質を明らかにするとともに社会状況の変化に対応した活用の方法や生活者の新しい関わり方によるマネージメント手法について研究を行っています。
(大阪公立大学ホームページより)
人生と都市を魅力的にする「パブリックライフ」について研究しています。UR都市機構、兵庫県立人と自然の博物館を経て、現職。共著書に『シビックプライド』『いま、都市をつくる仕事』『都市を変える水辺アクション』ほか。共訳書に『パブリックライフ学入門』 (武田先生のTwitterアカウントより)
武田先生のお話から街や都市についての、新しい視点について学んでもらいます。
★魅力的なまちとはどのようなまちなのか、住みやすいまちとの違いは何だろうか。
★コミュニケーションをデザインするとは
★パブリックライフをデザインするとは
自分自身はどう思うか、また豊かな人生を歩むためにまちはどう関わるのか、何よりどんな街に住みたいか、意見をまとめてみましょう。そうすればイメージがつかみやすくなり、講演への理解も深まると思います。
講演をきくにあたっては、講師の方は講演のために準備をされて来られますので、せっかくの機会に、ここでしかできない質問、この先生にしか聞けない質問をしましょう。きちんと理解したうえでの質問、聞かれた側がどう受け取るかという想像力を働かせることが必要です。
本日の課題
武田先生の研究の中で、興味を持った内容または質問したい内容をグーグルフォームに記入してください。武田先生にも事前に共有しますので、先生の講演に組み込んでもらえるかもしれません。せっかくなのでこの先生にしか聞けない質問がいいですね。先生の書籍、また紹介するリンクを参照してください。
https://book.gakugei-pub.co.jp/campaign/covid-19_takeda/ コロナ関連特別寄稿
https://citylabtokyo.jp/2020/09/18/200920-eventreport-aiba-takeda/ City Lab Tokyo



