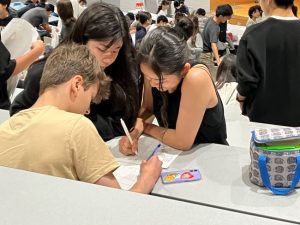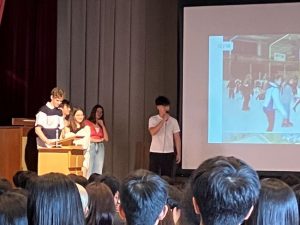SSS(高校1年生)武田重昭先生の講演「街の魅力とは」/ パネルディスカッション
- 2023.06.09
- 授業
 第3回目の講座では、大阪公立大学の武田重昭先生をお招きして講義をしていただき、そして本校の生徒たちとパネルディスカッションをさせていただくという大変貴重な時間を持ちました。武田先生は緑地計画学(Landscape Architecture)を専門に研究され、多くのまちづくりの実例を通してシビックプライドの構築について書籍や多くの講演等で発信を続けておられます。本校にお越しいただくのは3年目となりましたが、今回も生徒たちの質問に事前に目を通していただき、講演のご準備をしてくださいました。
第3回目の講座では、大阪公立大学の武田重昭先生をお招きして講義をしていただき、そして本校の生徒たちとパネルディスカッションをさせていただくという大変貴重な時間を持ちました。武田先生は緑地計画学(Landscape Architecture)を専門に研究され、多くのまちづくりの実例を通してシビックプライドの構築について書籍や多くの講演等で発信を続けておられます。本校にお越しいただくのは3年目となりましたが、今回も生徒たちの質問に事前に目を通していただき、講演のご準備をしてくださいました。
● 武田重昭先生の講演 「持続可能なまちづくりについて」
講演の中で武田先生は次のような問いかけについて話してくださいました。
◎ 理想のまちってどんなまちですか?
◎ パブリックライフで私たちの暮らしは豊かになりますか?
◎ なぜシビックプライドが必要なのですか?
◎ 多様な価値観をどうやってまちに活かすことができますか?
これらの問いかけに対する先生のお話の中で印象に残ったことをご紹介します:
☆ “パブリックライフを育むのは“人”。
パブリックライフとは、公共空間で他者と直接的・間接的にかかわりを持ちながら過ごす社会的な生活のことを言います。川が流れる美しい自然環境にWifiを設置してリモートワークができるようにした徳島県神山町の実例があります。人口が減少している集落に人の暮らしをもってくることで、そのまちを変えていくことができます。
☆ “10,000人の1回より100人の100回を!”
賑わいや盛り上がりを求めて大規模なイベントを1回だけ開催するよりも、小規模なイベントを、回数を増やすことで日常的な出来事とし、出会いのきっかけを増やすことでまちはより魅力的となります。昨日より今日、今日より明日が少しずつよくなるといったことがずっと続くまちのほうが、最終的にはいいまちになると考えられます。
☆ “まちをつくるのは、市民のまちに対する誇りや愛着!”
現在の大阪城は市民の寄付によって再建されたものです。また市立吹田市サッカースタジアムは市民や企業からの寄付金などで建設されています。自分たちでこのまちを良くするんだ、という自負心や気概が大切であり、それによってまちに対する誇りや愛着、シビックプライドが生まれます。この誇りや愛着こそがまちの魅力の根幹であり、まちの原動力、そして持続可能性に必要なものであるといえます。
☆ “まちの魅力となり持続可能なまちをつくるのはあなたです!”
誰かにつくってもらうのではなく、自分たちがつくることで、まちのことをもっと好きに、もっと身近に、もっと自分のこととして、感じられるようになります。
〈講演を聴き終えて〉
武田先生の講演を聴き、魅力的で持続可能なまちをつくるのは私たちひとりひとりであるという意識が高められました。また生徒からの質問にも丁寧にお答えいただき、学生の私たちがどのようにまちづくりに関わることができるか、数々のヒントを得ることができました。コロナ禍で大きく社会が変化した今、先生の研究に基づく考え方は私たちが豊かな暮らしを送るための大切な気付きとなり、これからのまちづくりに向けて私たちが大きく一歩を踏み出すきっかけとなったのではないでしょうか。
● パネルディスカッション
 武田先生の講演の後、生徒たちがパネラーとなり、生徒から出されたテーマについてパネルディスカッションを行いました。生徒たちはまちづくりに対する考えや意見を活発に交換し、武田先生からも貴重な意見を伺うことができました。
武田先生の講演の後、生徒たちがパネラーとなり、生徒から出されたテーマについてパネルディスカッションを行いました。生徒たちはまちづくりに対する考えや意見を活発に交換し、武田先生からも貴重な意見を伺うことができました。
ここではディスカッション内容の一部をご紹介します。
パネラー①:
ゆったりと歩ける歩道をつくり、いろんな世代の人が散歩をしてあいさつや会話ができるスペースをつくったらいいと思います。
パネラー②:
車がなくても生活しやすいまち、子育て世代は学校や病院が近くにあるまち、若者世代はカラオケや娯楽施設が近くにあるまちなど、世代によって求めているものが違います。私は、いろんなものがひとつの場所に集まった建物を作れば、いろんな世代のニーズに応えられるのではないかと思います。
武田先生:
みなさんが話してくれたのはローカルシティの取り組みです。歩いて暮らせるまち、例えばパリは“15 minutes city” や、メルボルンは“20 minutes city”と言われるように、歩いて15分または20分圏内に、生活の身の回りの必要な機能が集まっている都市を目指しましょうという取り組みです。今までは機能に分化した施設、例えば高齢者のために施設、子供のための施設、買い物の施設などを車で行ける範囲に作るまちづくりをしていました。
しかしコロナ禍になってから、遠くに行くよりは、近くで身の回りの暮らしの環境がよくなるようにまちを作る動きに変わってきています。世代を超えていろんな人が共通してもっている、心地よく感じられるまちをつくることが大切であると考えます。
パネラー①:
繋がりたくない人に繋がりを強制しなくてもいいと思います。しかし、お年寄りや子育て世代は繋がりを求めていると思います。マンションの公共スペースや地域のお祭りなど、その人たちが一歩踏み出してコミュニケーションをとることができるような場所をつくることは大切だと思います。
パネラー②:
私は、魅力的なまちを作るという観点からは、ある程度人とのかかわりが必要であると思います。よりよい街を作るためには、まず住民自身が自分たちの街のことをよく知る必要があると思います。たくさん地域の方々と触れ合うことで、街のいいところも、課題となるところもわかって、シビックプライドが高まることにも繋がっていくと思います。私は京田辺市に12年間住んでいて、京田辺が大好きです。小学校のころに田植え体験や公園巡りなど、地元の方々と交流できる校外学習がありました。全てのひとと家族のような関係を築く必要はないと思いますが、同じところに住んでいる人との共通点をみつけて、その人を認識することが大切であると思います。
武田先生:
コミュニティには「テーマ型コミュニティ」と「支援型コミュニティ」があります。阪神大震災のときに、支援型コミュニティが残っていたから人々は助け合うことができました。特に若い人たちにとって支援型コミュニティは必要ないと思われる人もいると思いますが、高齢者や子育て世代のように遠くに行くことが困難であったり、インターネットでつながるだけでは困る人たちがいます。その人たちにとっては「遠くの親戚より近くの他人」と言われるように、近くで助けてくれる人が必要になってくる場面があります。将来そのようなことがあることをみなさんも想像してみてください。例えばマンションのエントランスで高齢の方に声をかけてみると、彼らも喜んでくれるのではないかと思います。
パネラー①:
私は海外と日本の学校のどちらにも通った経験があります。日本では小学生のときにまち探検をしますが、自分のまちのことを学習するのは小学校までだったと思います。私がタイに住んでいるときは、小学校だけに限らず授業の中で地域のイベントが紹介されるなど、地域について話す時間があり、そのようなところに違いがあるのではと感じています。
パネラー②:
私は日本の学校と海外でインターナショナルスクールに通っていました。日本では社会科見学や職場体験などキャリアを優先した学習が多かったのですが、インターでは美術館や博物館、公園などに足を運んだり、学校周辺を歩く遠足や、芸術に触れる機会がありました。私は幼い頃からのこのような教育によって違いが生まれると思いました。
武田先生:
これは難しい質問ですが、日本は単一民族国家であることが影響しているのではないかと思います。全員同じ民族なので、国というまとまりの単位はあるけど、都市としてのまとまりを感じにくいのではないでしょうか。また日本は(いい意味で)
平和で豊かな自然があって、八百万の神と呼ばれる自然を敬う文化があるのに対して、ヨーロッパでは、もしかしたら相手は敵かもしれなくて、“自分たちの都市は自分たちで作っていかないといかない“という自負心があり、文化的な背景としてのモチベーションは日本とヨーロッパでは違うと感じます。近代化が進んだ現在は、日本も西洋の精神に学んで新しい都市づくりを重ねていくことも重要であると思います。
パネルディスカッションでは生徒たちは高齢者や子育て世代の視点にたって考え、SDGsに掲げる「だれも取り残さない持続的なまちづくり」をすすめることに意識を向けて意見を述べました。また多くの帰国子女が通う本校において、様々な国での経験談を交えて意見を交換することができ、日本だけでなく世界の国々の魅力的なまちづくりについて考える機会を得ることができました。
また、武田先生や先生の研究室生からもお話やご意見を伺うことができ、魅力的で持続可能なまちづくりについてさらに興味を深めることができました。本日は私たちのために貴重なお話をしてくださりありがとうございました。
本日は、ドイツ交換プログラムで本校に留学中の生徒たちも参加しました。
「いろいろな街の魅力を見つけよう!」のアクティビティに参加し、本校生徒と自分たちの住むまちについて情報交換しました。また壇上では映像を使って、現在通っているドイツの学校や住んでいるまちの紹介をし、プレゼンテーションをしてくれました。
コロナ禍によりしばらく途絶えていた留学生との対面での交流でしたが、プログラムの再開で直接交流をすることができ、生徒たちにとって良い刺激となり、有意義な時間となりました。